食物繊維とは?食物繊維で腸内環境は改善できる




食物繊維とは、食物に含まれる、人の消化酵素では消化することができない成分のことを指します。食物繊維にお通じを整えるイメージを持っている方も多いのではないでしょうか。
食物繊維にはお通じを整える以外にも様々な働きがあり、身体の調子を整えるのに役立ちます。
食物繊維の種類や働きを知って、健康的な生活を目指しましょう。
食物繊維とは、食べ物の中に含まれている、小腸で消化・吸収することのできない物質のことです。体の中で良い働きをすることが注目され、第6の栄養素ともいわれています。
食物繊維の働きとして多くの人に知られているのが、お通じを整えることでしょう。食物繊維は便のかさを増やしたり腸内細菌のエサとなり、腸内環境を整える善玉菌を増やす働きがあります。お通じは女性に多い悩みの一つですが、食物繊維を適切に摂ることで、お通じを整えることが期待できます。
また、食物繊維はお通じを整えるだけでなく、糖質の吸収をおだやかにしたり、脂質やナトリウムを吸着し排出をサポートする働きなどもあり、様々な健康効果が期待されています。
このように、食物繊維は体にうれしい働きがありますが、サプリメントやドリンクなどから摂る時は過剰摂取に十分注意し、毎日の食事とうまく組み合わせて不足を上手に補いましょう。
食物繊維には様々な種類がありますが、大きくは、水に溶けない「不溶性食物繊維」と水に溶ける「水溶性食物繊維」の2種類に分けられます。
「繊維」という名前から、糸状の、いわゆる繊維状のものを想像される方も多いのではないでしょうか?食物繊維には、繊維状のものだけではなく、水状のものや、ネバネバしたものもあります。
それらの違いは、「不溶性食物繊維」と「水溶性食物繊維」を判断する一つの基準です。
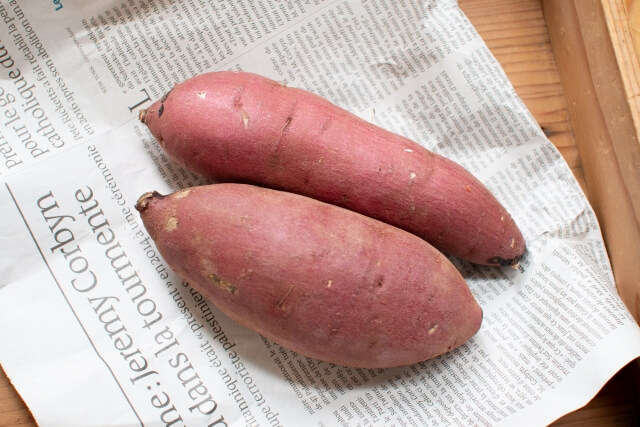
不溶性食物繊維は、便のかさを増やす役割を持っています。腸の運動を活発にし、お通じを整えてくれます。
また、水溶性食物繊維は、腸内環境を整えることや食後血糖値の上昇をおだやかにする働きがあります。
それぞれの食物繊維の中にも様々な種類があり、不溶性食物繊維には、セルロースやヘルセミロース、リグニン、キチン、キトサンなどがあります。
それらの不溶性食物繊維は、いもなどの穀類や豆類、野菜、甲殻類の殻、きのこなどに含まれています。

水溶性食物繊維には、ペクチンやグルコマンナン、アルギン酸、アガロース・アガロペクチン・カラギーナン・ポリデキストロースなどがあります。
それらの水溶性食物繊維は、わかめなどの海藻類、果物類や、ねばねばした野菜に多く含まれます。
また、水溶性食物繊維の中では、粘度が高いものと低いものがあります。
粘度が高いものには、ペクチン、グアーガム、グルコマンナンなどがあり、粘度が低いものには、難消化性デキストリン、イソマルトデキストリンなどが挙げられます。
日本人の食事摂取基準(2020年版)では食物繊維は一日あたり18~64歳で男性21g以上、女性18g以上を目標に摂取することが勧められています。また、不溶性食物繊維と水溶性食物繊維は2:1で摂取するのが理想といわれています。
50年ほど前では食物繊維の摂取量は目標値を超えていましたが、近年の日本人の食物繊維摂取量は14g前後と減少傾向がみられていました。令和元年に実施された国民健康・栄養調査によると、1日一人当たりの食物繊維の摂取量の平均は、男性は19.4g(そのうち不溶性食物繊維が11.8g、水溶性食物繊維が3.6g)、女性は17.5g(そのうち不溶性食物繊維が11.2g、水溶性食物繊維が3.5g)と、目標摂取量に近づいてきています。
食物繊維の総量としては目標摂取量に近づいてはいますが、摂取量が不足していることに変わりはありませんので、意識して食物繊維の摂取を続けましょう。
また、食物繊維の摂り方については、不溶性と水溶性をバランスよく摂ることが重要です。なぜなら、不溶性食物繊維と水溶性食物繊維はその働きに違いがあるからです。
不溶性食物繊維は便のかさを増やして老廃物の排出を促しますが、摂りすぎると腸に停滞しお通じを悪化させることもあります。水溶性食物繊維には腸内の善玉菌を増やしたり、食後血糖値の上昇をおだやかにする働きがあります。
これらの働きを十分に発揮するために、不溶性食物繊維と水溶性食物繊維の理想的なバランスは不溶性:水溶性が2:1とご紹介しましたが、食物繊維の摂取量の平均からみると、水溶性食物繊維が特に不足しています。
水溶性食物繊維が豊富に含まれる食品は少ないため、普段の食生活の中では意識的に水溶性食物繊維を摂取する必要があります。
水溶性食物繊維の多い身近な食材としては、大麦(100g当たり4.3g)、納豆(1パック50gの場合、1.2g)、キウイ(1個100gの場合、0.6g)があります。手軽に取り入れられる水溶性食物繊維の多い食材を普段の食生活にプラスして食物繊維のバランスを整えていきましょう。

冒頭でも述べたように食物繊維は腸内環境を整える作用があります。食物繊維が発酵すると腸内が弱酸性になり、善玉菌がすみやすくなります。
特に、水溶性食物繊維は善玉菌のエサになるだけでなく、善玉菌を増やしてくれます。善玉菌には消化・吸収、免疫などをサポートする働きがあり、健康維持のために大きく関わります。
近年では、飲酒や偏った食生活、睡眠不足、ストレスにより、腸内細菌のバランスを崩しやすい人が多くなっています。食物繊維は5大栄養素ではありませんが、体の健康に深く関係しており、腸内環境を整え、お通じよくする上で欠かせない成分です。
規則正しい生活をするとともに、バランスの良い食事と食物繊維を積極的に摂取することを心掛け、腸内環境を改善していきましょう。
管理栄養士免許、NR・サプリメントアドバイザー資格保有。
大学卒業後、サプリメントのOEM企画開発の会社に入社。機能性成分や商品作りのプロセスについて学ぶ。その後、株式会社メタボリックに転職し、商品企画開発室にて様々な商品を企画開発中。

管理栄養士 T